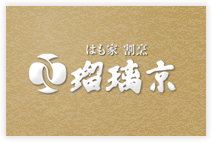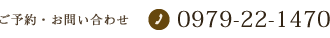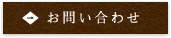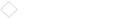1600年、細川忠興・忠利父子が39万9千石の藩主として中津に入城します。
1604年、忠興は今井浦(現在の行橋市今井)から腕利きの漁師たちを強制的に中津市小祝に移住させ、その結果、他の地方ではあまり食されない鱧がさかんに食されるようになります。そして、中津の料理人たちの手で次々に新しい鱧料理が開発され、中津の漁獲高は飛躍的に向上していきます。
このことは、中津近海の漁にも大きな影響を及ぼし、粉島(山口県徳山市)の漁師たちの間では「はも漁、、はもの骨切りの開祖は豊前中津小祝の漁師たちだ」という口伝が残されています。なかでも「はもチリ」は中津の多くの人々に深く愛され、「はもチリ」を食べるお膳のことを「チリ台」と呼ぶほどでした。以下のことから、中津での「はもチリ」発展の理由がうかがえます。
- 各家庭に「橙」の木が植えられ、秋口、橙酢をしぼり保存していた(チリ酢)
- 俗謡に高瀬にんじん、湯屋ねぶか、相原だいこん、和間はくさいと唄いこまれていた(チリ材料)
- 藩庁が生産制限を出すほど豆腐の消費量が著しかった
- 醤油は甘口が主流な九州の醤油に比べ、少し塩味が強くなりました(チリに最適)